「特定の宗教はないけれど、祈る気持ちは大切にしたい」あなたへ|SBNRという新しい心のあり方

「特定の宗教を信じているわけではないけれど、神社で手を合わせたり、故人を想って静かに祈ったりする時間も大切にしたい」。このように感じた経験は、あなたにもありませんか。
実は、この記事を書いている私自身も、そうした感覚を抱える一人です。いわゆるSBNRを自認していますが、朝夕には欠かさず小さな仏壇に手を合わせています。しかし、それは宗教的な義務感からではありません。むしろ、自分自身の現在の気持ちや考えを整理し、静かに自分と向き合うための「対話の時間」だと捉えているのです。
私たちの周りには、本当にたくさんの人が存在し、その数だけ多様な考え方や、いろいろな宗派の宗教があります。どれを選択するのかは、もちろんその人自身の自由です。だからこそ、「こうあるべきだ」という考え方を押し付けるのではなく、あなた自身のこころが思うまま、スッと腑に落ちる感覚を何よりも大切にしてほしい。私は心からそう願っています。
普段は意識していなくても、「あなたの信仰は?」と問われると「無宗教です」と答えながら、心に浮かぶ小さな違和感。この記事では、そんなあなたの気持ちに優しく寄り添いながら、SBNRとは何か、そして言葉の本当の意味について、私の経験も交えながら深く掘り下げていきます。
この記事が、形式にとらわれない祈りや、自由で心豊かなご供養を通じて、あなただけの「私の心の拠り所」を見つけるお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。特定の信仰とは異なる、あなただけの心の持ち方を探る旅へ、ご一緒に出発しましょう。
この記事で分かること
- SBNRという言葉の正確な意味と、運営者自身の解釈
- 「無宗教」という言葉が持つ違和感の正体と、SBNRとの本質的な違い
- 運営者の実体験から見る、SBNR的な祈りや供養の具体的な形
- 自分の感覚を信じ、心穏やかに生きるためのヒント
まず知りたい「SBNR とは」 – “無宗教”とは違う、あなたの心に寄り添う価値観
- 「Spiritual But Not Religious」- 言葉の本当の意味
- 「無宗教」と口にするときの、小さな違和感の正体
- なぜ日本人にSBNR(スピリチュアルな感覚)が馴染みやすいの?
- SBNRは「良いとこ取り」? – 誤解されやすいポイントと、その本質
- 「信じる」対象がなくても大丈夫。SBNRが肯定してくれる、今のあなたの気持ち
「Spiritual But Not Religious」- 言葉の本当の意味

まず、基本に立ち返ってみましょう。SBNRとは、「Spiritual But Not Religious(スピリチュアル・バット・ノット・リリジャス)」という英語のフレーズの頭文字を取った言葉です。これを日本語にすると、「宗教的ではないけれど、スピリチュアル(精神的)である」といった意味合いになります。
もう少し具体的に解説すると、これは制度化された特定の宗教団体や、その教義・戒律・儀礼には帰属しない、という明確なスタンスを示しています。教会やお寺に定期的に通ったり、決められた経典を学んだりすることはありません。一方で、目には見えない世界の存在や、人間を超えた大いなる何か、そして何より自分自身の内面に存在する精神性といった「スピリチュアルな事柄」に対しては、深い関心と敬意を抱いている状態を指します。
私自身の感覚で言えば、これは「外側」に答えを求めるのではなく、「内側」の感覚を信じる生き方、ということです。例えば、壮大な自然の風景を前にしたとき、ただ「綺麗だ」と感じるだけでなく、自分の存在の小ささや、生かされていることへの感謝のような、神聖な気持ちが湧き上がってくる。あるいは、素晴らしい音楽や芸術作品に触れたときに、理屈を超えて魂が揺さぶられ、涙が溢れてくる。これらもまた、SBNRの感覚に非常に近い体験だと私は考えています。
このように考えると、SBNRは特定の神や教えを「信じる」ことではなく、個人の内面で起こる様々な経験や感覚そのものを尊重する、極めてパーソナル(個人的)な心のあり方なのです。誰かに与えられた物差しではなく、自分自身の感覚という羅針盤を頼りに、精神性を探求していく生き方。それが、私が理解するSBNRの基本的な考え方であり、このブログを通じてお伝えしたい価値観の根底にあります。
「無宗教」と口にするときの、小さな違和感の正体

あなたは、法事や少し改まった場で、「ご自身の宗派は?」と尋ねられた経験はありませんか。その際に、「特にありません」「無宗教です」と答える方は、現代の日本では決して少なくないでしょう。私自身も、かつてはそう答えていました。しかし、その言葉を発した後に、どうも心が落ち着かないというか、自分の気持ちを正確に表現できていないような、小さな違和感を覚えていたのです。
この違和感の正体は、おそらく「無宗教」という言葉が持つニュアンスにあるのだと思います。この言葉は、多くの場合「神仏や精神的な世界への関心が全くない、合理的な人間である」といった、やや冷たく、乾いた印象で受け取られがちです。
しかし、実態はどうでしょうか。多くの日本人は、お盆にご先祖様をお迎えし、クリスマスを家族で祝い、新年には神様に昨年一年の感謝と新しい年の幸せを願って初詣に行きます。私自身もそうです。これらの行為を、単なる文化的なイベントとして楽しんでいるだけ、と言ってしまえばそれまでかもしれません。ただ、そこには確かに、目には見えない存在への感謝や畏敬の念、つまり「祈りの心」が込められているのではないでしょうか。
SBNRと、一般的に使われる「無宗教」、そして哲学的な立場である「不可知論」との違いを改めて整理してみると、その立ち位置がより明確になります。
| 観点 | SBNR (精神的だが無宗教) | 無宗教 (非宗教的) | 不可知論 |
| 精神性への関心 | 高く、積極的に探求する | 個々人で異なる(関心がない場合も多い) | 探求の対象ではなく、判断を保留する |
| 宗教組織への所属 | しない | しない | しない |
| 神や超越者の存在 | 個人的な解釈で信じる・感じることがある | 信じない、または関心がないことが多い | 存在を「知り得ない」という知的な立場を取る |
| 祈りや儀式 | 自分の価値観に基づいた形で行うことがある | 行わないことが多い | 行わない |
この表からも分かるように、SBNRは単に宗教組織に属していないというだけでなく、精神的な探求を個人的な形で行うという、より積極的で主体的な姿勢を示します。
もし、あなたが「無宗教」という言葉を使うたびに、ご自身の感覚とのズレを感じていたのだとすれば、それは「精神的なものを大切にする心」を、あなた自身が確かにお持ちだからに他なりません。その大切な感覚に、SBNRという名前を与えてみることで、これまで抱えていたモヤモヤが、すっと晴れていくかもしれません。
なぜ日本人にSBNR(スピリチュアルな感覚)が馴染みやすいの?

世界的に見ても、日本はSBNR的な価値観を持つ人が非常に多いと言われています。私自身、この感覚は多くの日本人にとって、ごく自然なものなのではないかと感じています。その背景には、私たちの国が長い時間をかけて育んできた、独特の歴史や文化、そして宗教観が存在していると考えられます。
その根底にあるのが、古来から続く自然崇拝、いわゆるアニミズム的な思想です。これは、特定の神様だけを崇めるのではなく、雄大な山や清らかな川、道端の大きな岩や古い木といった、自然界のあらゆる万物に神や霊が宿ると考える世界観です。この思想は、神道の源流ともなっています。特定の教祖や厳格な経典を持つというよりは、私たちの暮らしのすぐそばにある自然への畏敬の念が、日本人の精神性の基盤を静かに、しかし確かに形作ってきました。
私たちが季節の移ろいに敏感で、桜の開花に心を躍らせ、紅葉の美しさに感動するのは、単に風景として楽しんでいるだけではないのかもしれません。無意識のうちに、そこに宿る生命の輝きや、神聖なものを感じ取っているからではないでしょうか。
また、日本の宗教史における「神仏習合」も、SBNR的な感性を育んだ大きな要因です。大陸から仏教が伝来した際に、元々日本にあった神道の神々と仏様が争うのではなく、お互いを認め合い、時には同一視されながら共存していくという、非常に柔軟な形で受け入れられました。家の中に仏壇と神棚が共に祀られていたり、お寺の境内の中に鳥居が立っていたりするのは、その何よりの証拠です。
言ってしまえば、唯一絶対の神を信仰するという一神教的な価値観よりも、「八百万(やおよろず)の神」という言葉に象徴されるように、様々な存在の中に神聖さを見出し、状況に応じて自然に手を合わせるというスタイルが、私たち日本人には文化的な遺伝子として深く染みついているのです。
だからこそ、「特定の宗教団体には所属していないけれど、精神的なものを大切にしたい」というSBNRの考え方が、多くの日本人にとって、海外から入ってきた新しい概念というよりは、むしろ「昔から持っていた自分の感覚に、ようやく名前が付いた」という感覚で、ごく自然に受け入れられるのだと私は思います。
SBNRは「良いとこ取り」? – 誤解されやすいポイントと、その本質

SBNRという考え方についてお話ししていると、時折「それは単なる“良いとこ取り”なのではないか」「厳格な修行や戒律から逃げているだけで、自分勝手なのでは?」といったご意見をいただくことがあります。これは、SBNRという生き方を考える上で、非常に重要な問いだと私は思います。
確かに、SBNRは特定の宗教が持つ戒律や義務からは自由です。しかし、それが「何でもあり」の自己中心的な考え方かと言えば、決してそうではありません。むしろ、その逆だと私は考えています。SBNRの本質は、「外的な規範がないからこそ、より高い内的な規範、つまり自分自身の良心や倫理観が問われる生き方」なのです。
宗教における戒律や教義は、信じる人々が道を踏み外さないように導く、いわばガードレールの役割を果たしています。SBNRには、この外的なガードレールがありません。だからこそ、自分自身の行動や選択の一つひとつに、自分で責任を持たなければなりません。他者への思いやり、誠実さ、自然環境への配慮といった普遍的な倫理観を、誰かに強制されるからではなく、自分自身の内なる声に従って実践していくことが求められます。
また、「良いとこ取り」という批判は、SBNRが他者の信仰に対して敬意を払っていない、という誤解に基づいている場合があります。しかし、真のSBNRは、多様な価値観を尊重します。世の中には様々な宗教があり、それぞれが人々にとってかけがえのない心の拠り所となっている。その事実を深く理解し、敬意を払うからこそ、自分もまた、自分の信じる道を静かに歩むのです。他者の信仰を否定したり、軽んじたりすることは、SBNRの精神とは相容れません。
私自身、様々な宗教の教えや哲学に触れることがありますが、それは「良いとこ取り」をしたいからではありません。それぞれの教えの中に、時代や文化を超えて受け継がれてきた人間の叡智や、普遍的な真理のかけらを見出し、それを自分の生き方の参考にさせていただきたい、という謙虚な気持ちからです。
このように考えると、SBNRは決して楽な道ではなく、むしろ自分自身の精神性と常に向き合い続ける、覚悟のいる生き方とも言えます。それは、自由であることの責任を引き受ける、成熟した大人のための価値観なのかもしれません。
「信じる」対象がなくても大丈夫。SBNRが肯定してくれる、今のあなたの気持ち

「何かを強く信じなければ、心の拠り所は得られないのではないか」「確固たる信仰がない自分は、精神的に未熟なのではないか」。現代社会を生きる中で、このように漠然とした不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、周囲に熱心な信仰を持つ方がいる場合、その確信に満ちた姿と自分を比べてしまい、焦りを感じることもあるでしょう。
しかし、どうか安心してください。SBNRという考え方は、そのような不安からあなたを優しく解き放ってくれます。SBNRが最も大切にするのは、「何を信じるか」という“対象”そのものではなく、「自分がどう感じるか」という“内なる声”に深く耳を澄ませることだからです。
絶対的な答えや、全ての人が従うべき教義が存在しないからこそ、あなた自身の正直な感覚や、これまでの人生で得てきた経験を信頼することが、全ての出発点になります。
例えば、あなたが亡きお祖母様との思い出が詰まった場所を訪れたとき、ふと温かい気持ちに包まれ、まるで見守られているかのような感覚を覚えたとします。その時、その感覚を「きっとお祖母ちゃんが見守ってくれているんだ」と、ただ素直に受け止める。ここに、小難しい宗教的な解釈や、科学的な証明は一切必要ありません。あなた自身が確かに感じたその気持ちこそが、何よりも尊い、あなただけの「スピリチュアルな体験」なのです。
私自身も、明確に「神様」や「仏様」といった存在を人格的に信じているかと問われると、即答はできません。しかし、美しい夕焼けを見た時に感じる、言葉にならないほどの感謝の念や、先祖代々の繋がりの中に自分がいるという感覚は、確かに存在します。私は、この「よく分からないけれど、確かに在る」という感覚そのものを、自分の心の拠り所として大切にしています。
SBNRという価値観は、時に「確固たる信仰を持たないこと」への罪悪感や、周囲との違いから生じる疎外感から、私たちの心を救ってくれます。信じる対象が明確でなくても、あるいはその対象が他人から見れば非科学的なものであっても、あなたの心が安らぎや温かな繋がりを感じるのであれば、それはあなたにとっての、かけがえのない真実です。SBNRは、そのように多様で個人的な精神性のあり方を、「そのままでいいんだよ」と、優しく、そして力強く肯定してくれる価値観なのです。
「SBNR とは」具体的にどう生きること? – 供養や終活で大切にしたい、あなたらしい祈りのカタチ
- 形式にとらわれない「祈り」– 自然との対話や、静かに自分と向き合う時間
- SBNRの視点で考える、自由で心豊かな「ご供養」のヒント
- 心の羅針盤を持つということ – なぜ「自分の感覚」が大切なのか
- 終活で向き合う「私の心の拠り所」– エンディングノートに書きたいこと
- 親戚や周囲との関係 – 信仰について、誠実に気持ちを伝えるには
形式にとらわれない「祈り」– 自然との対話や、静かに自分と向き合う時間

SBNRの考え方を暮らしの中に具体的に取り入れる第一歩は、「祈り」という行為を、特別な儀式としてではなく、日常の中にある静かな時間として捉え直すことから始まります。決まった作法や場所にこだわる必要は、全くありません。
冒頭で少し触れましたが、私自身は毎朝と毎夕、小さな仏壇に手を合わせる習慣があります。SBNRを自認しているのになぜ仏壇が?と不思議に思われるかもしれません。私にとってこの時間は、特定の宗派の教義に則った宗教行為ではないのです。むしろ、これは一日の始まりと終わりに、自分自身と対話し、心を整えるための、かけがえのない「メディテーション(瞑想)」の時間です。
朝は、新しい一日を無事に迎えられたことへの感謝を伝えます。そして、「今日は穏やかな心で過ごせますように」「人に対して優しくあれますように」と、自分自身の行動指針を静かに確認します。夕べには、「今日も一日、無事に過ごさせていただき、ありがとうございました」と感謝し、その日にあった出来事や、自分の感情の動きを振り返ります。嬉しかったこと、少し悲しかったこと、反省すべきだったこと。それらをただジャッジするのではなく、「そう感じたんだね」と、もう一人の自分が受け止めてあげるような感覚です。この数分間の対話が、私の心をリセットし、明日への活力を与えてくれます。
もちろん、これはあくまで私個人のやり方です。あなたにとっての祈りは、全く違う形かもしれません。 例えば、朝起きて窓を開け、ベランダの植物に水をやりながら、その生命力に触れ、新鮮な空気を吸い込む。その一連の行為が、あなたにとっての一日の始まりの感謝の祈りになるでしょう。 また、通勤途中の公園で、いつも同じ場所に佇む大きな木に心の中で挨拶をしたり、美しい夕焼け空に一瞬だけ立ち止まって心を寄せたりする時間も、自然という大いなる存在との、静かで豊かな対話と言えます。
さらに、自分自身の内面と深く向き合うことも、重要な祈りの時間となります。 好きな音楽をヘッドフォンで聴きながら、その世界に没入する。あるいは、一日の終わりに数行でも日記を書き、自分の感情を言葉にして整理してみる。または、何も考えずにただ呼吸に意識を集中させる瞑想にふける時間を持つのも、素晴らしい方法です。 こうすることで、日々の喧騒や情報過多の中で見失いがちだった、自分自身の本当の気持ちや、心の奥底にある願いに気づくことができます。
SBNR的な祈りで最も大切なのは、「こうしなければならない」というあらゆる固定観念から、自分を解放してあげることです。あなたが「ああ、心が安らぐな」「満たされるな」と感じるその瞬間こそが、あなたにとっての、最も尊い祈りの時間なのです。
この考え方は、当ブログ「『こうあるべき』という気持ちは、少しだけ横に置いて。あなただけの自由な祈りで、心をふわりと軽くするお話」がとても参考になります。こちらもぜひ読んでみてくださいね。
SBNRの視点で考える、自由で心豊かな「ご供養」のヒント

故人を想い、弔う「供養」という行為も、SBNRの視点を取り入れることで、形式的な義務感から解放され、より自由で、心豊かなものへと変わっていきます。伝統的な儀礼を軽んじるわけではなく、むしろその本質を理解した上で、自分らしい表現方法を見つけていく、というアプローチです。
私が考える供養の本質とは、突き詰めれば「故人を忘れず、感謝を伝え、その存在を自分の心の中に生き生きと留め続けること」にあります。この本質に立ち返ったとき、お墓参りや年忌法要といった伝統的な形式以外にも、数えきれないほどの供養の形があることに、私たちは気づくはずです。
故人の好きだったものを、共に分かち合う
これは、私自身もよく実践する方法です。例えば、お酒が好きだった父の命日には、父が好きだった銘柄の日本酒を仏壇にお供えし、その後自分も同じものを少しだけいただきます。「お父さん、今年もこの季節が来たよ。一緒に一杯やろうか」と心の中で語りかけながら過ごす時間は、私にとって父との再会の時間です。 故人が好きだった料理を家族で作って食べたり、大切にしていた音楽を聴いたりするのも、素晴らしい供養になります。生前の思い出を語り合いながら、「きっと今もこの場所で、一緒に笑ってくれているね」と感じる温かな時間に、故人との精神的なつながりは、より一層深まっていきます。
故人との思い出の場所を訪れ、対話する
旅が好きだった母を想い、母とよく一緒に出かけた海辺の町を、時々一人で訪れます。特別なことをするわけではありません。ただ、昔二人で歩いた砂浜を歩き、同じカフェでコーヒーを飲む。その風景の中に母の面影を探し、共に過ごした時間に想いを馳せることで、物理的な距離や時間の隔たりを超えた、静かな心の対話が生まれるのです。
もちろん、前述の通り、伝統的な供養の形を否定する必要は全くありません。お墓を綺麗に掃除し、新しいお花を供え、静かに手を合わせることで心が落ち着き、故人との繋がりを実感できるのであれば、それはあなたにとって何よりも意味のある尊い行為です。
重要なのは、その行為にあなたの心が伴っているかどうか、ということです。SBNR的な供養とは、世間体や義務感から行うものではなく、故人を想うあなたの純粋な気持ちから自然に生まれてくる、全ての愛情深い行いであると、私は考えています。
心の羅針盤を持つということ – なぜ「自分の感覚」が大切なのか

この記事を通して、私が繰り返しお伝えしたいメッセージがあります。それは、「あなた自身の感覚を、何よりも大切にしてほしい」ということです。これは、SBNRという生き方の核であり、変化の激しい現代社会を、心穏やかに生きていくための、最も重要な「心の羅針盤」になると、私は信じています。
なぜ、それほどまでに「自分の感覚」が大切なのでしょうか。 それは、情報が溢れかえり、多様な価値観が交錯する現代において、「外側」に確固たる答えを求めることが、非常に困難になっているからです。かつては、地域社会や特定の宗教、あるいは国といった大きな共同体が、人々に生き方のモデルや善悪の基準を提供してくれていました。しかし、現代を生きる私たちは、無数の選択肢の中から、自分自身の生き方を自らデザインしていくことを求められています。
このような時代に、他人の意見や世間の常識、流行といった「外側の声」にばかり耳を傾けていると、私たちは自分の人生の航路を見失ってしまいます。「〇〇さんが良いと言っていたから」「みんながそうしているから」という理由で選択を繰り返していると、やがて「本当の自分は何を望んでいるのだろう?」という、根本的な問いに答えられなくなってしまうのです。
「自分の感覚を大切にする」とは、決してわがままに生きるということではありません。それは、静かな場所で、自分の心の声に真摯に耳を傾ける訓練です。何かを選択する時に、「これをしたら、心が温かくなるか、軽くなるか?」「それとも、何となく重く、苦しくなるか?」と、自分自身に問いかけてみる。頭で考えた損得勘定ではなく、身体や心が発する微細なサインを感じ取るのです。
最初は、その声はとても小さく、聞き取りにくいかもしれません。しかし、意識的に耳を傾ける練習を繰り返すうちに、その感覚はどんどん研ぎ澄まされていきます。そして、その「スッと腑に落ちる」感覚に従って下した決断は、たとえ結果がどうであれ、深い納得感を伴います。なぜなら、それは他の誰でもない、「自分自身が選んだ道」だからです。
この「心の羅針盤」を持つことで、私たちは他者の多様な生き方を、心から尊重できるようにもなります。「私には私の感覚があるように、あの人にはあの人の感覚がある」ということが、腹の底から理解できるからです。他者の選択をジャッジするのではなく、ただ「あなたは、そう感じるのですね」と受け止めることができる。この姿勢こそが、真の多様性の尊重に繋がっていくのだと、私は考えています。
もし「自分の感覚」の受信が難しいと感じるようなら、マインドフルネスの技法を試してみてください。当ブログ「ざわつく心を鎮めたい初心者の方へ。祈りのように実践する、マインドフルネスのやさしいやり方」を読むと、ヒントが得られるかもしれません。
終活で向き合う「私の心の拠り所」– エンディングノートに書きたいこと
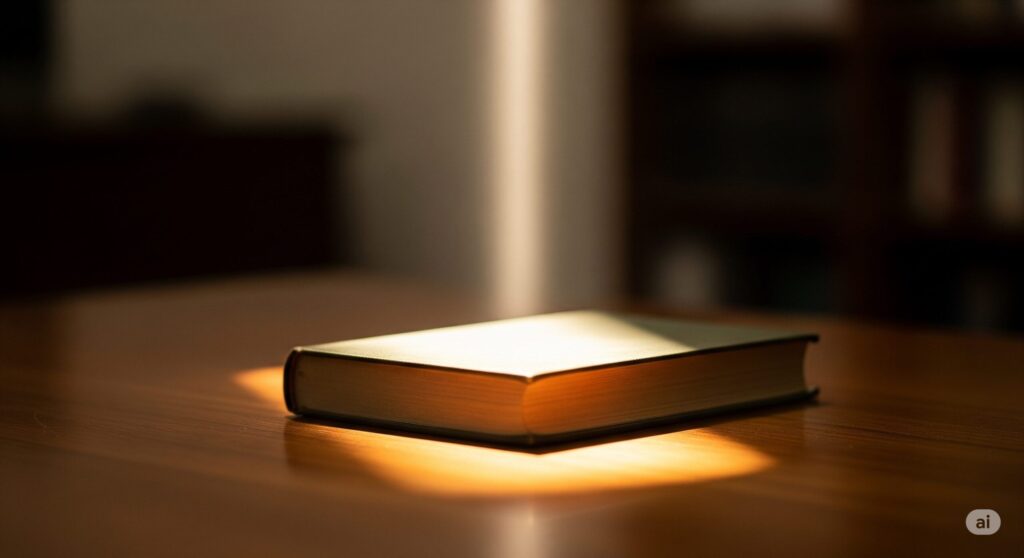
人生の終わりを見据え、今をより良く生きるための活動である「終活」。これは、まさにSBNRの考え方と深く、そして密接に関わる営みです。なぜなら、終活とは単なる物理的な身辺整理や事務手続きの準備ではなく、「自分が人生で何を大切にしてきたのか」「どのような心の状態で、人生の最終章を迎えたいのか」という、自分自身の精神性の核心と向き合う、尊いプロセスだからに他なりません。
この、自分自身の内面を深く掘り下げる旅において、非常に有効なツールとなるのがエンディングノートです。財産や相続、葬儀の希望といった事務的な項目を埋めることはもちろん大切です。しかし、それ以上に、SBNR的な視点から「あなた自身の心の拠り所」について、言葉を尽くして書き記しておくことを、私は強くお勧めします。
もし、私自身がエンディングノートを書くとしたら、きっと以下のような項目を設けるでしょう。これは、残される家族へのメッセージであると同時に、自分自身の人生を振り返り、肯定するための作業でもあります。
- 私の人生で、心が震えるほど感動した風景や体験 (例:初めて訪れた京都の竹林の静けさ、子供が生まれた瞬間の産声、など)
- 心を落ち着けたい時、何度も繰り返し聴いた音楽や、読んだ本 (具体的な曲名や書名を記し、なぜそれに惹かれたのかも少し書き添える)
- 私が人生の指針としてきた、大切にしている言葉や哲学 (誰かの名言でも、自分なりの信条でも良い)
- 私の人生に関わってくれた、全ての人への感謝の言葉 (特定の人へのメッセージだけでなく、これまで出会った全ての人への感謝を記す)
- もしもの時、私の最期の空間に置いてほしいもの (家族の写真、お気に入りの絵葉書、庭で摘んだ一輪の花など、ささやかなもので良い)
- 私の弔い方についてのお願い (堅苦しい儀式よりも、皆で私の好きだった音楽を聴きながら、思い出話で笑ってほしい、など)
- 私の人生観・死生観について (死をどう捉えているか。恐れではなく、自然な循環の一部と考えている、など)
- 最後に伝えたいこと (「どれかの考え方を押し付けるのではなく、自分のこころが思うまま、スッと腑に落ちる自分の感覚を大切にして生きていってください」といった、自分の根源的な願いを記す)
これらの問いに一つひとつ答えていく作業は、自分自身の価値観や精神性の輪郭を、改めてなぞり、確認していく旅です。特定の宗教的な信仰がなくても、自分にとって何が「聖なるもの」で、何が心の支えとなってきたのか。それが、驚くほど明確になっていくでしょう。
そして、この記録は、残される家族にとって、お金や物では代えがたい、かけがえのない「心の遺産」となります。彼らがあなたの死後に悲しみや戸惑いの中にいるとき、このノートを開けば、そこに生き生きとしたあなたの声を聞き、あなたが大切にしてきた世界観に触れることができる。それは、あなたの望む穏やかな最期の時間を尊重し、そして彼ら自身が前を向いて生きていくための、大きな力となるはずです。
親戚や周囲との関係 – 信仰について、誠実に気持ちを伝えるには

SBNRという、自分自身の感覚を大切にする生き方を選択する上で、避けては通れないのが、親戚や周囲の人々との関係性です。特に、ご家族やご親族の中に、特定の信仰を深く、そして大切にされている方がいる場合、法事への参加の仕方や、ご自身の考えをどのように伝えればよいか、心を悩ませる場面があるかもしれません。
私自身も、親族との集まりの中で、こうしたテーマについて考える機会が何度かありました。その経験から学んだことは、ここで最も大切なのは、「否定」ではなく「尊重」から入ること。そして、「対立」ではなく「対話」を心がける、という姿勢です。
一方的に「私は宗教というものを信じないので」と、線を引くような言い方をしてしまうと、相手は自分の大切な価値観を否定されたように感じ、心を閉ざしてしまいかねません。そうではなく、まずは相手の信仰心そのものへの敬意を、誠実な言葉で伝えることから始めるのが良いでしょう。
例えば、「お義母さんが、長年にわたってご先祖様を大切にされ、信仰を守ってこられたこと、心から尊重しています。そのお気持ちは、本当に尊いものだと思っています」というように、まずは相手の価値観を肯定するメッセージを伝えます。
その上で、「ただ、私自身は、少し考え方が違いまして。特定の宗教団体に所属するという形ではなく、自分なりのやり方で故人への感謝や敬意を表したい、と考えているのです」と、穏やかに、そして正直に、ご自身のスタンスを伝えてみてはいかがでしょうか。ここで、SBNRという専門用語をあえて使う必要はありません。「私なりのやり方」という、柔らかく、個人的な表現を用いることで、相手も受け入れやすくなります。
もちろん、一度でスムーズに理解を得られるとは限りません。その場合は、これを「対立」の始まりと捉えるのではなく、お互いをより深く理解するための「対話」の機会と捉え直すことが求められます。何よりも注意すべきは、相手が大切にしている信仰や儀式を、決して軽んじたり、揶揄したりするような言動は厳に慎むことです。たとえ自分がそれを信じていなくても、それが相手にとっては、人生を支えるかけがえのない心の拠り所であるという事実を、決して忘れてはなりません。
そして、具体的な歩み寄りとして、自分にできる形で関わる姿勢を示すことも、良好な関係を維持するためには非常に有効です。例えば、法事の読経の時間は静かに末席で控えさせていただくけれど、その後の会食の席では、誰よりも積極的に故人の思い出話を語り、場を和ませる。あるいは、お墓の掃除や準備は、率先してお手伝いさせていただく、といった形です。
あなたの誠実な対話の姿勢と、故人を敬う具体的な行動が伴えば、信仰の形は違っていても、その根底にある「大切な人を想う心」は、きっと通じ合うはずです。
まとめ
この記事では、「SBNR とは」という問いを入り口に、その言葉の本当の意味から、私自身の経験や考え方を交えながら、日々の暮らしや供養、終活の中にその価値観をどう取り入れていくかについて、深く掘り下げてきました。
長い文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。最後に、あなたがあなた自身の感覚を信じ、心穏やかに生きていくための大切なポイントを、改めてまとめます。
- SBNRとは「宗教的ではないが、精神的である」という個人の内面を尊重する心のあり方
- 私にとってSBNRは、外側に答えを求めず、自分の内なる声に従う生き方のこと
- 「無宗教」という言葉への違和感は、あなたが精神性を大切にしている証
- 日本人は古来の自然観や神仏習合の歴史から、SBNR的な感性が馴染みやすい
- SBNRは「良いとこ取り」ではなく、自らの良心に従う、内的な規範が問われる生き方
- 仏壇に手を合わせる行為も、宗教儀式ではなく、自分との対話の時間と捉えることができる
- 信じる対象が明確でなくても、自分の「温かい」「腑に落ちる」という感覚こそが真実
- 祈りとは特別な儀式ではなく、日常の中にある感謝や、自然と向き合う静かな時間
- 供養の本質は故人を忘れず感謝することであり、その表現方法は無限に存在する
- 故人の好きだったものを分かち合い、思い出を語らうことも尊い供養の形
- 終活とは、自分自身の「心の拠り所」を見つめ直し、人生を肯定するプロセス
- エンディングノートには、事務的な事柄だけでなく、あなた自身の人生観や哲学を記してほしい
- 周囲との関係では、相手の信仰への敬意を忘れず、誠実な対話を心がけることが大切
- 「こうあるべき」という考えを手放し、自分のこころが思うままの感覚を信頼する
この記事が、あなたが自分らしい祈りと生き方を見つける、ささやかなきっかけとなれば幸いです



