ざわつく心を鎮めたい初心者の方へ。祈りのように実践する、マインドフルネスのやさしいやり方

慌ただしい毎日の中で、ふと心が過去の出来事に囚われたり、まだ来ぬ未来への不安でいっぱいになったりすることはないでしょうか。他の人には些細なことに見えるかもしれませんが、「自分の考え方は間違っているのではないか」「自分は誰かに迷惑をかけているのではないか」という思考が、頭の中を支配してしまう。
その程度のことは誰でも考えることだ、と頭では理解しようとしても、心の奥深くで脈打つ感情がそれを許してくれない。夜、静寂が訪れると、かえって心のざわめきは大きくなり、夢を見ることさえ怖くて、疲れ果てて眠りに落ちるまで延々とネガティブな思考を繰り返してしまう。
もし、あなたがこのような苦しさを少しでも感じているのなら、それは決してあなただけが特別なのではありません。実は、私自身もまた、長年にわたって心の置き場所に悩み続けてきた一人です。この記事では、マインドフルネスを単なる技法としてではなく、自分自身の心と体を慈しみ、評価しない心で向き合う、祈るように静かな時間として捉え直します。
少し個人的な話にもなりますが、私がマインドフルネスと出会い、どのように心のざわめきと向き合えるようになったのか、その体験も交えながらお話しさせてください。ご紹介するのは、日常でできる簡単な4ステップです。この記事を読み終える頃には、マインドフルネスを毎日の暮らしに取り入れ、習慣にするためのヒントもきっと見つかるはずです。
この記事でわかること
- マインドフルネスが「祈りの時間」である理由
- 心がざわつく仕組みと、それを鎮める考え方
- 初心者でも今日から実践できる具体的なやり方
- 無理なくマインドフルネスを続けるためのコツ
マインドフルネスとは、自分と向き合う「祈りの時間」。初心者でもわかるやさしいやり方
- マインドフルネスは「評価しない」練習
- 私たちはいつも、頭のなかで何を考えている?
- 「今、ここ」に意識を向けるとは?
- 祈るように、自分の心と体を慈しむ
マインドフルネスは「評価しない」練習

マインドフルネスの核心は、一言でいえば「評価しない」練習にあります。私たちは日々の生活の中で、無意識のうちに目の前で起こる出来事や自分自身の感情、思考の一つひとつに「良い・悪い」「好き・嫌い」「正しい・間違い」といったレッテルを貼り、常に自分や他者を何らかの基準で測っています。
例えば、「会議でうまく発言できなかった自分はダメだ」とか、「不安を感じてしまうなんて、心が弱い証拠だ」と考えてしまうことはないでしょうか。これらは全て、自分自身に対する厳しい評価です。マインドフルネスは、そうした自動的に、そして半ば強迫的に行われる評価の癖にふと気づき、一度立ち止まるための時間となります。
少し、私の話をさせてください。
私の育った家庭には、幼い頃から父親という存在がいませんでした。そして、母親の愛情はもっぱら兄に注がれ、私の存在はまるでそこにないかのように扱われることが日常でした。今でいう「毒親」という言葉が、おそらく当てはまると思います。家庭は、本来であれば無条件の安心感を得られる場所のはずですが、私にとっては常に「自分はここにいて良いのだろうか」と存在価値を問われる場所だったのです。
「良い子」でいれば、褒められるかもしれない。「悪い子」であれば、叱られるかもしれない。しかし、私にはそのどちらもありませんでした。関心を向けられないということは、「評価」の土俵にすら上がれないということです。良いも悪いもなく、ただ「無」として扱われる経験は、私の自己肯定感を根底から揺るがしました。自分という存在が、まるで色のない透明人間のように感じられたのです。
だからこそ、私は他者の評価に敏感な人間に成長しました。誰かに認められることで、自分の存在価値を確かめようと必死だったのです。しかし、他者からの評価は非常に移ろいやすく、それを求め続けることは、終わりのない渇きに水を注ぎ続けるような苦しみを伴います。
マインドフルネスが「評価しない」練習であると知ったとき、最初は戸惑いました。評価されることでしか自分を認識できなかった私にとって、評価を手放すことは、自分が自分でなくなるような恐怖さえ感じさせたのです。しかし、実践を続けるうちに、その本当の意味が少しずつ分かってきました。
マインドフルネスは、快い感情も、不快な感情も、どちらが優れていると判断しません。ただ、ありのままの事実や感情を、そのまま受け止めるのです。良い悪いという判断の物差しを一旦傍らに置き、ただ「今、自分はこう感じているのだな」と、静かに見つめる。この態度は、他者からの評価という不安定な基盤の上に自分の価値を置くのではなく、自分自身の内側に、揺るぎない安心の場所を育てることに他なりません。それは、誰かに認めてもらう必要のない、自分自身への無条件の優しさにつながっていくプロセスなのです。
私たちはいつも、頭のなかで何を考えている?
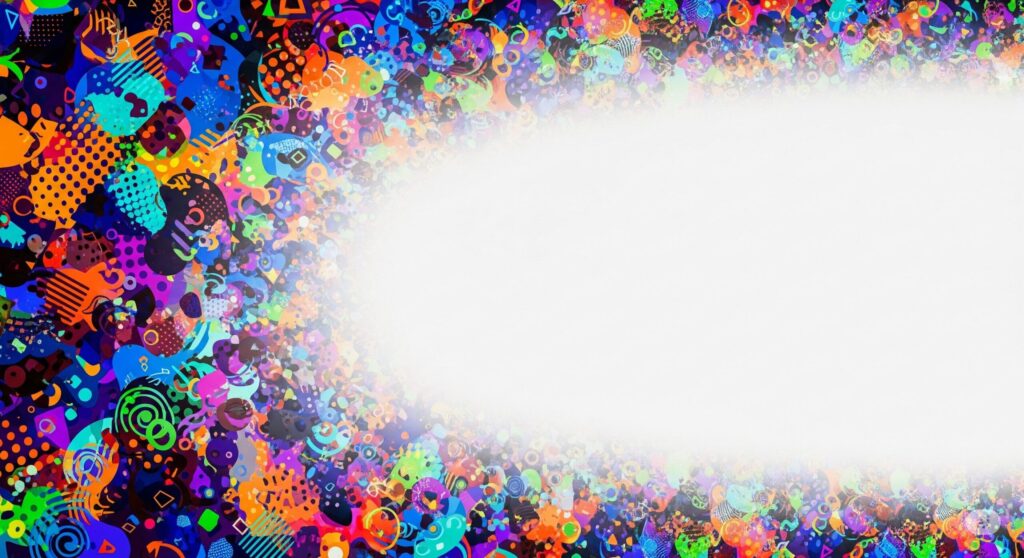
私たちの心は、何も意識していないと、まるで蝶のようにひらひらと、絶え間なくさまよい続けます。数分前の出来事を悔やんだかと思えば、数時間後の予定を心配し、昨日の会話を思い出しては、来年の計画に思いを馳せる。このように、心が「今、この瞬間」から離れて過去や未来をさまよう状態は「マインド・ワンダリング(心の放浪)」と呼ばれています。
実際、ハーバード大学の研究では、人が起きている時間の47%もの間、目の前のこととは違う何かを考えて過ごしているという結果も出ています。この心の放浪が、創造的なアイデアを生んだり、未来の計画を立てたりと、有益に働くこともあります。しかし、多くの場合、特に心が疲れているとき、その内容は過去への後悔や未来への不安といった、ネガティブなものに偏りがちです。
そして、この状態が長く続くほど、心のエネルギーは知らず知らずのうちに消耗していきます。車で言えば、エンジンをかけっぱなしで、しかもアクセルを何度も空ぶかししているようなものです。これが、理由のわからない焦りや、慢性的な疲れ、そして心のざわつきの大きな原因となります。
私の場合、このマインド・ワンダリングは、特に苦痛を伴うものでした。私の頭の中を支配していたのは、常に「自分の考え方は間違っているのではないか」「自分は誰かに迷惑をかけているのではないか」という、自分を疑い、他者におびえる思考のループです。
それは、幼少期に母の顔色をうかがい、自分の存在が許されるかどうかを常に探っていた頃の、古い心の癖の現れでした。愛されているという実感、無条件に受け入れられているという安心感を持てなかった私は、「ありのままの自分ではダメだ」というメッセージを、自分自身に深く刻み込んでしまったのです。そのため、私の心の放浪は、決して楽しい空想の旅ではありませんでした。むしろ、過去の傷を再体験し、未来に起こりうる拒絶を延々とシミュレーションする、苦しい時間だったのです。
多くの人にとっては何でもない他者の言動が、私には自分への否定のように感じられる。良かれと思ってしたことが、誰かを不快にさせたのではないかと何日も思い悩む。論理では「考えすぎだ」と分かっているのに、感情がそれを否定し、不安の渦から抜け出せなくなります。
あなたがもし、自分でもコントロールできない思考のループに悩み、心のざわつきを感じているのであれば、それは心が「今」にいないサインかもしれません。そして、その思考の内容には、あなたが生きてきた歴史や、満たされなかった思いが色濃く反映されている可能性があるのです。
「今、ここ」に意識を向けるとは?

それでは、「今、ここ」に意識を向けるとは、具体的にどのようなことなのでしょうか。これは、頭の中で渦巻く思考のドラマからそっと抜け出して、五感で直接感じられる、生々しい現実に注意を戻すことを意味します。
私の心が過去や未来をさまよっていたとき、私は現実の身体感覚や、周囲の環境に対してほとんど意識を払っていませんでした。心はいつも、幼少期の寂しさの中か、あるいは他者から否定されるかもしれない未来の不安の中にあったのです。現実は、ただ通り過ぎていくだけの背景に過ぎませんでした。
マインドフルネスは、この流れを意識的に断ち切る試みです。例えば、一杯のお茶を飲む時間を想像してみてください。以前の私なら、きっと「昨日のあの言い方はまずかったかな」「明日のプレゼン、大丈夫かな」などと考えながら、味も香りも感じずに飲み干していたでしょう。
しかし、「今、ここ」に意識を向けると、全く違う世界が立ち現れます。
五感という錨(いかり)
- 視覚: 湯呑みの色やかたち、お茶の美しい水色(すいしょく)、立ち上る湯気の揺らぎを、初めて見るかのようにじっくりと観察します。
- 触覚: 指先に伝わる湯呑みのあたたかさ、陶器のなめらかな質感を感じます。
- 嗅覚: 鼻を近づけ、お茶の葉が持つ独特の、ほっとするような香りを深く吸い込みます。
- 味覚: お茶を一口含み、すぐに飲み込まず、舌の上でゆっくりと転がします。甘み、渋み、苦味といった複雑な味わいを丁寧に感じ取ります。
- 聴覚: 周囲の音に耳を澄ませます。もし静かなら、その静寂そのものを味わいます。遠くで聞こえる車の音や、自分の呼吸の音さえも、ただの音として認識します。
このように、五感の一つひとつに注意を向けることは、思考の嵐が吹き荒れる海から、現実という港に「錨(いかり)」を下ろすようなものです。心が過去や未来に流されそうになっても、この「今、ここ」にある身体感覚という錨があれば、私たちはいつでも現在の瞬間に戻ってくることができます。
他にも、窓から聞こえてくる雨の音に耳を澄ませたり、歩いているときの足の裏が地面に触れる感覚を確かめたり、風が肌をなでる感触に注意を向けたりすること。これら全てが、「今、ここ」にいるための素晴らしい練習になります。思考の渦から抜け出し、現実の感覚に安らぐことで、心は放浪をやめ、本来の静けさを取り戻すことができるのです。
祈るように、自分の心と体を慈しむ

マインドフルネスは、生産性を上げるためのライフハックや、心を無理やり無にしようとする精神修行ではありません。むしろ、どんな状態の自分であっても、ただ優しく受け入れる「祈りの時間」に近いものだと、私は考えています。
祈りとは、本来、何かを願い求めるのでなく、今ここにある命への感謝や、ありのままの自分を受け入れるための静かな対話の時間です。特に、私のように、自分自身に対して肯定的な感情を持つことが難しい人間にとって、この「祈り」という捉え方は、大きな救いとなりました。
率直に言って、「自分を慈しむ」「自分を愛する」という言葉が、私には長らく理解できませんでした。愛情を受けた記憶が乏しい人間にとって、自分を愛する、慈しむというのは、まるで馴染みのない外国語を話すような、途方もなく難しい課題に感じられたのです。「自分には慈しむほどの価値などない」という声が、いつも心のどこかから聞こえてきました。
しかし、マインドフルネスの実践は、この難解な課題への具体的なアプローチを示してくれました。例えば、実践中に雑念が浮かんできたとします。以前の私なら、即座に「また集中できない!なんて自分はダメなんだ」と自己批判を始めていたでしょう。これは、幼い頃から私に染みついた、自分を責めることでしか自分と関われなかった古い癖です。
マインドフルネスが教えてくれたのは、全く違う関わり方でした。雑念が浮かんできたら、それを敵視するのではなく、「ああ、今、こんなことを考えているのだな」と、親しい友人の話に耳を傾けるように、ただ優しく気づいてあげるのです。
呼吸が浅ければ、浅いままの呼吸と共にいてあげる。心が落ち着かなければ、落ち着かないままの心を、ただ静かに見守る。その状態を評価することなく、「今は、そうなのだな」と、ありのままを承認してあげる。この繰り返しが、私が生まれてから一度も経験したことのなかった、「自分自身に無条件で寄り添ってもらう」という体験そのものでした。
これは、誰かにやってもらうのではありません。自分自身で、自分に対して行うのです。この行為こそが、「自分を慈しむ」ということなのだと、私は実践を通じて学びました。それは、大げさな自己愛の言葉を自分に投げかけることではなく、今この瞬間の、たとえ不完全で頼りなく思える自分であっても、その存在を静かに肯定し、共にいてあげるという、ささやかで、しかし力強い「祈り」の行為なのです。
これを理解した上で実践することで、マインドフルネスは単なるストレス解消法から、自分自身の傷ついた心と和解し、自分の中に安全な場所を育んでいくための、神聖な時間へと変わっていくでしょう。
初心者でも簡単。日常でできるマインドフルネスのやり方4ステップ
- ステップ1:静かな場所で、楽な姿勢で座る
- ステップ2:呼吸に意識を集中させる
- ステップ3:雑念が浮かんでも、否定せずに受け流す
- ステップ4:5分から始めて、少しずつ時間を延ばしていく
- マインドフルネスを習慣にするためのヒント
ステップ1:静かな場所で、楽な姿勢で座る

マインドフルネスを始めるにあたり、まずは心が安らぐ環境を整えることから始めます。これは、自分自身のための聖域を作るような、大切な準備です。可能であれば、数分間、誰にも邪魔されずに過ごせる、静かで落ち着ける場所を選んでください。
それは、朝日が差し込む窓辺でも、お気に入りのソファの上でも、あるいはクローゼットの中のような少し閉ざされた空間でも構いません。大切なのは、物理的な静けさ以上に、あなたが「ここは安全だ」と感じられる心理的な安心感です。もし家族と住んでいて一人の時間を作るのが難しい場合は、「これから5分だけ静かにするね」と一声かけるだけでも、心の準備がしやすくなります。
次に姿勢ですが、これも「こうでなければならない」という厳格な決まりは一切ありません。雑誌やウェブサイトで見かけるような、背筋が伸びた完璧なあぐらのポーズを想像して、気後れしてしまう方もいるかもしれません。しかし、目的は体を鍛えることではなく、心を休ませることです。自分が最もリラックスできる姿勢を見つけることが、何よりも優先されます。
椅子に腰掛けるのが楽であれば、それがあなたにとっての正解です。その際は、足の裏が床にしっかりと着くように椅子の高さを調整すると、安定感が増します。床に座る場合は、お尻の下にクッションや座布団を敷くと、骨盤が安定し、腰への負担が軽くなります。
背筋は、無理にまっすぐ伸ばそうと意識しすぎると、かえって緊張を生んでしまいます。イメージとしては、頭のてっぺん(百会というツボのあたり)から、天井に向かって一本の透明な糸が伸びていて、その糸に頭全体が軽く吊り上げられているような感覚です。そうすると、背骨が自然なS字カーブを描き、力みのない、それでいてだらしなくない姿勢が取れます。
手は、膝の上に手のひらを上に向けても下に向けても、どちらでも構いません。あるいは、お腹の前でそっと重ねる(法界定印という形です)のも良いでしょう。色々と試してみて、腕や肩の力がすっと抜ける位置を探してみてください。
目は、完全に閉じるのが心地よければそれでも良いですし、もし眠ってしまいそうになったり、目を閉じるとかえって不安な気持ちが湧き上がってきたりする場合は、半眼(はんがん)もおすすめです。これは、視線を2メートルほど先の床の一点に、ぼんやりと落とす方法です。焦点を合わせず、ただ光を感じる程度にまぶたを下ろします。
服装も、体を締め付けるベルトや窮屈なジーンズなどは避け、ゆったりとしたリラックスできるものを選ぶと、より実践に集中しやすくなるでしょう。このように、一つひとつ自分の体の声を聞きながら、自分だけの心地よい「座る」かたちを整えること自体が、すでにマインドフルネスの始まりなのです。
ステップ2:呼吸に意識を集中させる

心地よい姿勢が整ったら、次に行うのは、私たちの命の源である「呼吸」へ、そっと意識を向けることです。ここで最も大切なのは、呼吸を一切コントロールしようとしない、という点です。私たちは普段、無意識のうちに呼吸をしていますが、いざ意識を向けると「深く吸わなければ」「長く吐かなければ」と、つい操作したくなってしまいます。
しかし、マインドフルネスにおける呼吸の観察は、評価や操作を手放す練習の一環です。今日の呼吸が浅くても、速くても、途切れ途切れでも、それで構いません。ただ、今この瞬間に起きているありのままの自然な呼吸を、好奇心を持った科学者のように、あるいは初めて見る不思議な現象を眺める子供のように、ただただ観察するだけです。
では、具体的にどこに意識を向ければよいのでしょうか。意識を向けるポイントは、人によって感じやすい場所が異なりますので、いくつか試してみて、ご自身が一番しっくりくるところを見つけてください。
呼吸を感じるためのアンカーポイント
- 鼻先: 空気が鼻の入り口を通り抜けるときの、わずかなひんやりとした感覚。そして、吐く息が触れるときの、少し温かい感覚。この温度差に集中するのは、非常に繊細で良い練習になります。
- 胸のあたり: 息を吸うと、胸郭が風船のように優しく広がり、吐くとしぼんでいく動き。洋服が擦れる感覚や、皮膚が伸び縮みする感覚に注意を向けます。
- お腹のあたり: 特に腹式呼吸を意識しなくても、息を吸うとお腹が自然に膨らみ、吐くとへこんでいく動き。手をお腹にそっと当ててみると、この動きを感じやすくなります。体の中心で起こる、この穏やかで力強いリズムは、心を落ち着けるための強力なアンカー(錨)となります。
もし、どこか一つの場所に集中し続けるのが難しいと感じたら、呼吸の全プロセスを追いかけるのも良い方法です。鼻先から入った空気が、喉を通り、気管を下り、肺いっぱいに広がり、そしてまた同じ道をたどって外に出ていく。この空気の旅路を、心の中で実況中継するように、ただただついていくのです。
まるで、浜辺に座って、寄せては返す波のリズムを飽きずに眺めているかのように、自分の呼吸という波を見守ります。この単純な作業に没頭していると、頭の中を駆け巡っていた思考の喧騒が、少しずつ遠のいていくのを感じられるかもしれません。
ステップ3:雑念が浮かんでも、否定せずに受け流す

マインドフルネスを実践していると、必ず、100%の確率で「雑念」が浮かんできます。「今日の夕飯どうしよう」「あの仕事、大丈夫かな」「さっき言われた一言が気になる」といった日常的なことから、過去の苦い記憶、未来への漠然とした不安まで、様々な思考が次から次へと現れるでしょう。
ここで、マインドフルネスを始めたばかりの人が最も陥りがちなのが、「ああ、また集中できなかった。自分には向いていないんだ」と、自分自身にダメ出しをしてしまうことです。そして、その自己批判が新たな雑念となり、負のループに陥ってしまうのです。
しかし、どうか覚えておいてください。雑念が浮かぶのは、あなたの意志が弱いからでも、集中力がないからでもありません。それは、私たちの脳が持つごく自然で正常な働きなのです。思考を生み出すのが脳の仕事ですから、静かに座っているからといって、その仕事が完全に停止することはありません。
したがって、マインドフルネスの目的は「無になること」や「雑念を消し去ること」ではないのです。本当の目的は、「雑念が浮かんできたことに、ただ気づく」という、その一点にあります。むしろ、雑念に気づけたこと自体が、マインドフルネスの練習がうまくいっている証拠であり、素晴らしい成功体験なのです。
私自身の話をすれば、実践中に浮かんでくる雑念の多くは、自己否定的なものでした。「どうせ私なんて、誰からも必要とされていない」「また間違ったことをしてしまうんじゃないか」という、幼い頃から抱えてきた馴染み深い思考です。初めのうちは、この声が聞こえてくるたびに、胸が苦しくなり、マインドフルネスどころではありませんでした。
しかし、練習を重ねるうちに、対処法が少しずつ変わってきました。思考そのものと戦うのをやめたのです。自己否定的な思考が浮かんできたら、その内容に深入りして「そんなことない!」と反論したり、「なぜこんなことを考えてしまうんだ…」と落ち込んだりするのではなく、一歩引いたところから、その思考を観察するのです。
雑念への優しい対処法
- 気づく: 「あ、今、『自分はダメだ』という考えが浮かんだな」と、心の中で優しく実況中継(ラベリング)します。
- 承認する: その思考を無理に追い払おうとせず、「そうか、そう考えているんだね」と、その存在を一旦認めてあげます。あたかも、不安を訴える小さな子供の話を聞いてあげるように。
- 手放す: そして、その思考を、空に浮かぶ雲が風に流されていくのを見送るように、そっと手放します。執着せず、追いかけず、ただ去っていくのに任せます。
- 戻す: 最後に、再び意識を、呼吸の感覚という「今、ここ」のアンカーへと優しく戻します。
この「気づいて、承認し、手放し、戻す」というプロセスを、評価や自己批判を交えずに、ただ淡々と、そして優しく、何度でも繰り返します。100回雑念が浮かんだら、100回呼吸に戻ればいいのです。この根気強い繰り返しこそが、思考の渦に巻き込まれずに、心の穏やかさを保つための、何よりのトレーニングとなるのです。
5分から始めて、少しずつ時間を延ばしていく

マインドフルネスを日々の暮らしに取り入れたい、と思ったとき、最初からあまりに高い目標を掲げてしまうと、かえって長続きしないことがあります。「毎日欠かさず30分間、完璧な瞑想をしなければならない」といった義務感は、やがてプレッシャーとなり、実践そのものが億劫になる原因にもなりかねません。
特に、心が疲れ切っているときや、自己肯定感が低い状態にあるとき、「できなかった自分」を責める材料を一つ増やしてしまうことにもなりかねません。それでは本末転倒です。
ですから、まずは、ご自身にとって「これなら絶対にできる」と思える、ごく短い時間から始めてみることを強くお勧めします。それは、1日にたった5分間かもしれません。もし5分でも長い、あるいは時間が取れないと感じるなら、1分や3分でも全く問題ありません。極端な話、3回深呼吸をするだけでも、それは立派なマインドフルネスの実践です。
大切なのは、実践の時間の長さや質の高さではなく、「意識的に自分のための時間を持ち、心と向き合う」という習慣を、生活の中に根付かせることなのです。短くても、毎日(あるいは週に数日でも)続けることで、心は少しずつ「立ち止まって、自分に気づく」というモードに慣れていきます。
スマートフォンのタイマーを5分にセットして、アラームの音はなるべく驚かないような優しいものを選びましょう。そして、時間が来るまでは、ただ座って呼吸に意識を向けます。時間が来たら、すぐに立ち上がらず、静かに目を開け、自分の体の感覚や、周りの光や音を少しだけ感じてから、ゆっくりと日常の動作に戻ります。
短い時間でも続けていくうちに、不思議な変化に気づくかもしれません。例えば、以前より少しだけ、自分の感情の波に早く気づけるようになったり、イラっとしたときに一呼吸おけるようになったり。あるいは、5分の実践が心地よく感じられ、「もう少しだけ、この静かな時間の中にいたいな」という気持ちが自然に湧いてきたりするでしょう。
そのように感じられたらしめたものです。そうなって初めて、自分の内側からの求めに応じて、少しずつ時間を7分、10分と延ばしていくのが、最も無理なく、そして楽しく続けるための鍵となります。
焦りは禁物です。マインドフルネスは、結果を出すための競争ではありません。効果を急ぐあまり、力んでしまっては、マインドフルネスがもたらす本来の恩恵である「ありのままを受け入れる」という感覚から遠ざかってしまいます。自分自身のペースを尊重し、今日の自分ができる範囲で、優しく実践することを心がけてください。
マインドフルネスを習慣にするためのヒント

ここまで、マインドフルネスの考え方と具体的なやり方について、私の体験も交えながらお伝えしてきました。この最後のセクションでは、この祈りのように穏やかな時間を、あなたの忙しい暮らしの中に無理なく根付かせるための、様々なヒントを箇条書きでご紹介します。全てを試す必要はありません。あなたが「これならできそう」と感じるものを、いくつか選んでみてください。
- 毎日同じ時間、同じ場所で行うと脳が習慣として認識しやすい
- 一日の始まりである朝起きてすぐ、あるいは一日の終わりである夜寝る前がおすすめ
- 歯磨きや食後の一杯のお茶など、すでにある生活習慣の直後に組み込む
- 最初から完璧な実践を目指さず、できなくても決して自分を責めない
- 雑念が浮かんでくるのは脳の正常な働きであると知っておく
- 雑念に「気づけたこと」自体が素晴らしい一歩だと捉える
- 自分が最もリラックスできる心地よい姿勢や場所を丁寧に探す
- やる気が出ない日でも「1分だけ座ってみる」ことを試す
- 「効果が出ない」と焦って結果を求めすぎないことが継続の秘訣
- お茶を飲む、音楽を聴くといった五感を使う日常の活動も立派なマインドフルネス
- 通勤中や散歩中に、足の裏の感覚に集中する「歩行瞑想」を取り入れてみる
- 実践後に感じたことや心の変化を、一言でもノートに書き留めてみる
- マインドフルネスを「自分を慈しむための、ささやかな祈りの時間」だと捉え直す
- 義務感から「やらなければ」と考えるのではなく「自分と向き合う時間を自分に贈ろう」と考える
- 何よりも大切なのは、自分自身のペースを尊重し、無理なく、長く続けていくこと
マインドフルネスは「祈りの時間」だとも捉えられます。特に、心がざわつく時のひとつの祈りの手法だと捉えると実践しやすいかもしれません。当ブログ「心がざわつく時の祈り|お守りになる言葉と祈りのレシピ」が参考になりますので、こちらの記事も読んでみてくださいね。



