手元供養のやり方|法律や宗派の注意点、残った骨の供養も解説

大切な方を亡くされた後、「故人をいつも身近に感じていたい」「離れがたい」というお気持ちから、ご遺骨を自宅で供養する手元供養のやり方に関心をお持ちではないでしょうか。
しかし、実際にどう進めればよいか調べる中で、さまざまな疑問が浮かんでくるかもしれません。例えば、手元供養では具体的に何を置くのか、どのようなメリットやデメリットがあるのか、そして法律や宗派に関する注意点はあるのか、といった点です。また、分骨した場合の遺骨の扱いや、残った骨の供養方法についても知っておく必要があります。
この記事では、失敗や後悔のないよう、手元供養の基本的な進め方から専門的な知識まで、分かりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- 手元供養の具体的なやり方と供養品の種類
- メリットやデメリット、選ぶ際の判断基準
- 法律や宗派に関する注意点と正しい知識
- 残った遺骨の適切な供養方法
初めてでもわかる手元供養のやり方と種類
- 手元供養のメリット・デメリットを解説
- 手元供養では具体的に何を置く?
- 主な手元供養品の種類と特徴
- 手元供養における遺骨の基本的な扱い
- 全骨と分骨の違いと必要な手続き
手元供養のメリット・デメリットを解説

手元供養を選択する前に、その利点と注意すべき点を理解しておくことが大切です。これにより、ご自身やご家族にとって最適な供養の形を見つける手助けとなります。
手元供養の最大のメリットは、故人をいつでも身近に感じられる点にあります。お墓が遠方にあったり、高齢でお墓参りが難しかったりする場合でも、自宅で日々語りかけ、手を合わせることができます。これは、大切な方を失った悲しみを癒し、心の支えとなるグリーフケアの効果も期待できます。また、お墓を新たに建立する場合と比較して、費用を大幅に抑えられることも大きな利点です。ミニ骨壺やアクセサリーなどの供養品は数万円から選ぶことができ、お墓の維持管理費もかかりません。
一方で、デメリットも存在します。手元供養は比較的新しい供養の形であるため、ご家族やご親族の中には「遺骨はお墓に納めるべきだ」という考えを持つ方もいらっしゃるかもしれません。後々のトラブルを避けるためにも、事前にしっかりと話し合い、理解を得ておくことが不可欠です。
もう一つの懸念点は、ご自身が亡くなった後、手元供養していた遺骨を誰が引き継ぎ、どのように管理するかという問題です。遺骨は法律上、自由に処分できないため、将来的な供養方法(お墓への納骨や永代供養など)をあらかじめ決めておかなければ、残された家族に負担をかけてしまう可能性があります。さらに、アクセサリーなどの小さな供養品は、紛失や盗難、災害による消失のリスクも考慮しておく必要があります。
これらの点を踏まえると、手元供養は故人を身近に感じられる心温まる供養方法である一方、長期的な視点での計画と周囲との合意形成が求められると言えます。
手元供養では具体的に何を置く?

手元供養には厳格な決まりはなく、故人を偲ぶ気持ちを最も大切にする供養方法です。そのため、何を置くかについても基本的には自由ですが、一般的に仏事の基本とされるお供え物を参考にすると、より心のこもった祈りの空間を作ることができます。
仏教では古くから「五供(ごく)」と呼ばれる5つのお供え物が基本とされています。
- 香(こう):お線香や抹香を指します。香りは故人の食事になると考えられているほか、場を清め、供養する人の心を落ち着かせる役割があります。
- 花(はな):生花をお供えします。美しい花の姿や香りは、故人の心を和ませると同時に、私たちの心も癒してくれます。季節の花や故人が好きだった花を飾るとよいでしょう。
- 灯燭(とうしょく):ロウソクの灯りです。仏の知恵や慈悲を象徴し、私たちの煩悩を照らし出す光とされています。安全に配慮して、火の取り扱いには十分注意してください。
- 浄水(じょうすい):清らかなお水やお茶をお供えします。故人の喉の渇きを潤すという意味合いがあります。
- 飲食(おんじき):炊き立てのご飯や、故人が生前好んだ食べ物、飲み物などをお供えします。
ただし、手元供養において、これら五供を毎日すべて揃える必要はありません。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で続けることが大切です。例えば、毎朝お水を取り替え、お線香を一本手向けるだけでも、立派な供養となります。
また、形式にとらわれず、故人の写真、愛用していた品、手紙などを一緒に飾るのも素敵です。写真立てを中心に、ミニ骨壺、小さな花瓶、そしてお気に入りの香りを焚くなど、自分らしい祈りのステージを自由に作り上げられる点が、手元供養の大きな魅力の一つです。
主な手元供養品の種類と特徴

手元供養を行う際には、ご遺骨を納めるための様々な供養品が用意されています。ご自身のライフスタイルや故人への想いに合わせて、最適なものを選ぶことができます。
ミニ骨壺
手のひらに収まるほどの小さな骨壺で、ご遺骨の一部を納めて自宅で安置するためのものです。デザインが非常に豊富で、陶器、真鍮、ガラス、木製など様々な素材から選べます。一見すると骨壺には見えないおしゃれなものが多く、リビングや寝室のインテリアにも自然に溶け込みます。悲しい気持ちになったときにそっと手に取り、故人に語りかけることで、心が落ち着くという方も多くいらっしゃいます。
遺骨アクセサリー
ご遺骨や遺灰を少量納めることができるペンダントやブレスレット、指輪などのアクセサリーです。常に身に着けていられるため、「故人とずっと一緒にいたい」という想いを叶えることができます。ペンダントトップの内部が空洞になっていてご遺骨を納めるタイプや、ご遺骨を樹脂で固めたり、ダイヤモンドなどの宝石に加工してあしらったりするタイプがあります。普段使いできるシンプルなデザインのものが多いのも特徴です。
ミニ仏壇・祈りのステージ
従来の大きなお仏壇とは異なり、現代の住環境に合わせて作られたコンパクトな仏壇や、飾り台のようなステージタイプのものも人気です。特定の宗派に縛られないモダンなデザインが多く、お部屋の好きな場所に自分だけの祈りの空間を設けることができます。ミニ骨壺やお写真、小さなお花などを自由に飾り、故人と向き合う大切な場所となります。必要な仏具がセットになった商品もあり、何を揃えればよいか分からない方にも便利です。
その他の供養品
上記以外にも、ご遺骨を納められるフォトフレーム(写真立て)や、可愛らしいぬいぐるみといったユニークな供養品もあります。来客時など、ご遺骨があることをあまり分からせたくない場合にも、さりげなく故人を偲ぶことができるため選ばれています。
手元供養における遺骨の基本的な扱い

手元供養を考える際、ご遺骨の扱いについて不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、法律的な問題や宗教的な観点について正しく理解しておくことが大切です。
まず、ご遺骨を自宅で保管する行為自体は、法律で何ら禁止されていません。「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」では、許可された墓地以外にご遺骨を「埋葬(土に埋めること)」してはならないと定められていますが、自宅の仏壇や棚の上などに「保管(安置)」することは、この埋葬には当たらないと解釈されています。したがって、ご遺骨を手元に置いて供養することは法的に全く問題ありません。
時折、「遺骨を手元に残すと成仏できない」「分骨すると体がバラバラになって故人が浮かばれない」といった声を聞くことがあります。しかし、これらは科学的・宗教的根拠のない俗説です。仏教の教えでは、故人の魂は四十九日を過ぎると次の世界へ旅立つと考えられており、魂がご遺骨そのものに宿っているわけではありません。
実際、仏教の開祖であるお釈迦様のご遺骨(仏舎利)は、亡くなられた後に弟子たちによって分骨され、世界各地の寺院や仏塔に祀られています。このことからも、分骨という行為が仏教的に禁じられているわけではないことが分かります。
供養において最も重要なのは、故人を敬い、偲ぶご遺族のお気持ちです。法律や俗説に惑わされることなく、ご自身が納得できる方法で、心を込めてご遺骨を扱うことが何よりも大切と言えます。
全骨と分骨の違いと必要な手続き
手元供養を行うにあたり、ご遺骨をどのように扱うかによって「全骨」と「分骨」の二つの方法があります。それぞれに特徴があり、必要な手続きも異なる場合があるため、違いを理解しておきましょう。
全骨(ぜんこつ)
全骨とは、火葬されたご遺骨の全てを手元に置いて供養する方法です。お墓に納骨せず、すべてのご遺骨を自宅などで安置します。この場合、一般的に火葬場で使用される6寸から7寸程度の大きさの骨壺をそのまま保管することになります。安置するためのある程度のスペースが必要になる点を考慮しなければなりません。もし、骨壺が大きすぎると感じる場合は、ご遺骨をパウダー状にする「粉骨」を行い、体積を小さくしてコンパクトな骨壺に移し替えるという選択肢もあります。
分骨(ぶんこつ)
分骨とは、ご遺骨の一部を手元供養のために残し、残りのご遺骨はお墓や納骨堂などに納める方法です。多くの方がこの分骨を選ばれます。ミニ骨壺やアクセサリーにご遺骨を納める場合、必要な量はごくわずかであるため、分骨が適しています。
分骨を行う上で最も注意すべき点は、ご遺族やご親族との合意形成です。ご遺骨の所有権は、祭祀を主宰する方(祭祀承継者)にあるとされています。分骨を希望する場合は、必ず事前に祭祀承継者や他のご親族とよく話し合い、全員の理解と同意を得ることがトラブルを避けるために不可欠です。
分骨に必要な手続き
手元供養のために分骨し、自宅で保管するだけであれば、法的な手続きや特別な許可は基本的に不要です。
しかし、分骨したご遺骨を、将来的に別の場所に納骨する可能性がある場合は、「分骨証明書」が必要になります。この証明書がないと、墓地や霊園で納骨を受け付けてもらえません。分骨証明書は、火葬の際に火葬場で発行してもらうのが最もスムーズです。もし火葬後に分骨を決めた場合は、すでにご遺骨を納めているお墓の管理者(寺院や霊園)に発行を依頼することになります。将来のことを見据え、念のため火葬の時点で分骨証明書を取得しておくと安心です。
手元供養のやり方で知るべき法律や注意点
- 手元供養の法律に関する基礎知識
- 知っておきたい宗派による考え方の違い
- 自宅保管で失敗しないための注意点
- 手元供養で残った骨の処分と供養方法
手元供養の法律に関する基礎知識
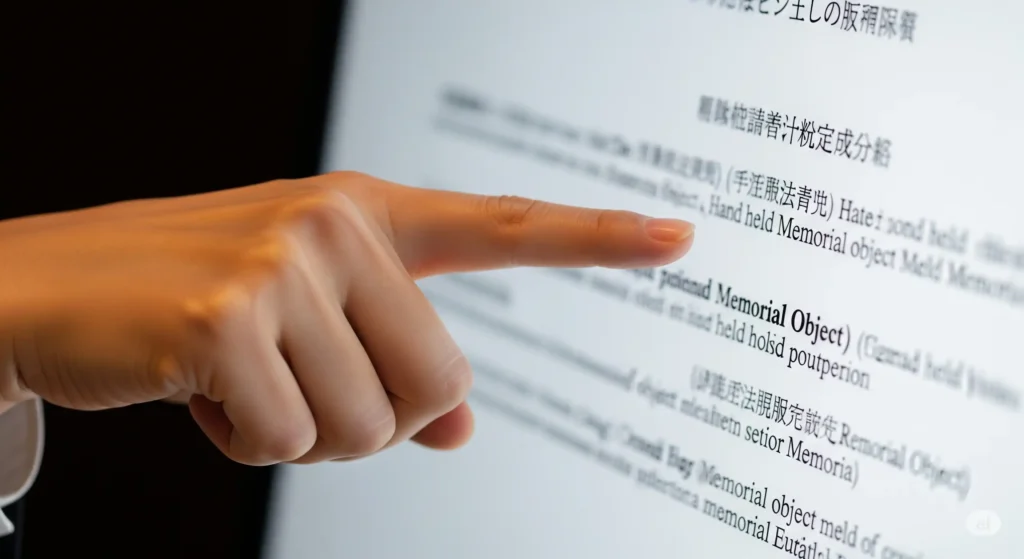
手元供養を検討する上で、「法律に触れないか」という点は多くの方が気になるポイントです。繰り返しになりますが、結論から言えば、ご遺骨を自宅で保管する手元供養は法律上、何の問題もありません。
日本の葬送に関する法律として「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「墓埋法(ぼまいほう)」があります。この法律の第四条には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定められています。
ここで重要なのは、「埋葬」や「埋蔵」という言葉の定義です。これらは「遺骨を土の中に埋めること」を指します。つまり、法律で禁止されているのは、許可を得た墓地以外の場所(例えば、自宅の庭や思い出の公園など)に遺骨を勝手に埋める行為です。
一方で、手元供養は遺骨をミニ骨壺やペンダントなどに入れて自宅の室内で「保管(安置)」する行為です。これは「埋葬」には該当しないため、墓埋法の規制対象外となります。したがって、ご遺骨を自宅に置いて供養することは完全に合法であり、誰かの許可を得る必要もありません。
同様に、ご遺骨の一部を分骨して手元に残すことも、法律上の手続きは不要です。
要するに、法律的な観点でのポイントは「土に埋めるかどうか」です。自宅の敷地内であっても、許可なくご遺骨を埋めると法律違反になるため、絶対にやめましょう。室内で大切に保管し、供養する限りにおいては、法的な心配は一切ないということです。この点を正しく理解しておけば、安心して手元供養を進めることができます。
知っておきたい宗派による考え方の違い

手元供養は、特定の宗教儀式に基づいたものではないため、基本的にはどのような宗教・宗派の方でも、あるいは無宗教の方でも自由に行うことができます。
仏教全体として、手元供養や分骨を明確に禁止する教えはありません。前述の通り、お釈迦様のご遺骨が分骨され、各地で大切に祀られている歴史が、その何よりの証左です。魂はご遺骨に宿るのではなく、四十九日を経て次の世界へ旅立つという考え方が一般的であるため、「ご遺骨を分けると成仏できない」という心配は不要と考えられます。
ただし、菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)がある場合は、少し配慮が必要になるケースがあります。お寺や住職の考え方によっては、納骨を前提としている場合や、分骨に対して慎重な姿勢を示す場合もゼロではありません。特に、そのお寺のお墓に納骨する際には、戒名をいただくことが慣習となっていることがほとんどです。
もし菩提寺との関係が深い場合は、手元供養を考えている旨を事前に住職に相談してみるのが望ましい対応です。故人への想いや手元供養を選びたい理由を丁寧に説明することで、理解を得やすくなるでしょう。
また、宗教的な教義というよりも、ご家族やご親族の中にある「慣習」や「考え方」への配慮が、実際にはより重要になることが多いです。特定の宗派に属していなくても、「遺骨は一つのお墓に納めるもの」という考え方が根強いご家庭もあります。手元供養は故人を想う気持ちを形にする素晴らしい方法ですが、それが新たな家族間の火種にならないよう、対話を重ね、皆が納得できる形を見つけることが大切です。
自宅保管で失敗しないための注意点

ご遺骨を自宅で大切に保管するためには、いくつかの注意点があります。特に「カビの発生」と「紛失」のリスクについて、あらかじめ対策を講じておくことが、後悔しないための鍵となります。
カビの発生を防ぐ
ご遺骨は、高温多湿の環境に長期間置かれるとカビが発生する可能性があります。日本の気候は湿気が多いため、保管場所には細心の注意が必要です。
カビを防ぐためのポイントは以下の通りです。
- 保管場所を選ぶ:直射日光が当たらず、風通しの良い場所を選びましょう。押し入れやクローゼットの中、水回り(キッチンや浴室)の近くは湿気がこもりやすいため避けるべきです。リビングや寝室の、空気の流れがある棚の上などが適しています。
- 密閉性の高い容器を選ぶ:手元供養品のミニ骨壺には、湿気の侵入を防ぐために蓋にシリコンパッキンが付いているものや、ネジ式でしっかりと閉まるものが多くあります。このような密閉性の高い製品を選ぶと安心です。
- 素手で触らない:ご遺骨を容器に移す際、素手で触れると手の湿気や雑菌が付着し、カビの原因になることがあります。可能であれば手袋を着用するか、清潔な乾いたお箸などを使用しましょう。
- 乾燥剤を活用する:骨壺の中に、シリカゲルなどの小さな乾燥剤を一緒に入れるのも効果的な対策です。
紛失・破損のリスクに備える
ミニ骨壺やアクセサリーはコンパクトな分、紛失や破損のリスクが伴います。
- 安置場所の安定性を確認する:ミニ骨壺などを置く棚や台が、地震などで倒れにくい安定した場所かを確認します。万が一の落下に備え、真鍮製など割れにくい素材の骨壺を選ぶという考え方もあります。
- アクセサリーの管理:遺骨ペンダントなどを日常的に身に着ける場合は、チェーンの留め具が緩んでいないか定期的に点検しましょう。また、温泉や入浴時には外すなど、劣化を防ぐための配慮も大切です。保管する際は、他のアクセサリーとは別の専用のケースに入れると紛失防止になります。
- 災害時の持ち出し:万が一の火災や水害、地震などの際に、どこに保管してあるかを家族で共有しておくことも重要です。すぐに持ち出せるよう、非常用持ち出し袋の近くに保管場所を決めておくのも一つの方法です。
これらの点に気をつけることで、大切なご遺骨を永く、清らかな状態で手元に保管することができます。
手元供養で残った骨の処分と供養方法

分骨によってご遺骨の一部を手元供養にした場合、残りのご遺骨をどのように供養するかを決める必要があります。ご自身の状況や故人の意向、ご家族の考えなどを踏まえて、最適な方法を選択しましょう。主な供養方法には以下のような選択肢があります。
- お墓への納骨先祖代々のお墓がある場合や、新しくお墓を建てる場合には、そちらに残りのご遺骨を納めるのが最も一般的な方法です。手元に一部を残しつつ、大部分はお墓で安らかに眠ってもらうという形は、多くの方に受け入れられやすいでしょう。
- 永代供養(えいたいくよう)お墓を継ぐ人がいない、あるいは子供に負担をかけたくないという場合に選ばれることが多い方法です。寺院や霊園が、ご家族に代わってご遺骨を永代にわたり管理・供養してくれます。他の人と一緒のお墓(合祀墓)に納骨される形が基本ですが、一定期間は個別に安置してくれるタイプもあります。
- 樹木葬(じゅもくそう)墓石の代わりに、桜やハナミズキなどの樹木を墓標として、その根元にご遺骨を埋葬する方法です。「自然に還りたい」という故人やご遺族の想いを反映できるため、近年人気が高まっています。多くは永代供養が付いており、継承者が不要な点も特徴です。
- 散骨(さんこつ)ご遺骨を2mm以下のパウダー状に粉骨し、海や山などの自然に還す方法です。特に海洋散骨がよく知られています。故人が海や山を愛していた場合に選ばれることがあります。ただし、散骨できる場所には条例による制限があるため、専門業者に相談・依頼するのが一般的です。散骨を行うとご遺骨は手元から完全になくなるため、一部を手元供養として残しておくことで、手を合わせる対象ができ、心の拠り所となります。
- 本山納骨(ほんざんのうこつ)信仰している宗派の総本山にご遺骨を納める方法です。宗派の開祖のもとで手厚く供養してもらいたいという想いから選ばれます。本来は信徒が対象ですが、宗派を問わず受け入れている本山もあります。一度納めるとご遺骨は返還されない合祀となるのが基本です。
これらの方法は、費用や管理方法、後からお参りができるかといった点でそれぞれ異なります。以下の表を参考に、じっくりと比較検討することをおすすめします。
| 供養方法 | 特徴 | 費用相場(目安) | メリット | デメリット |
| お墓への納骨 | 従来からの一般的な供養方法。墓石を建てて納骨する。 | 150万円~300万円 | 親族の理解を得やすい。お参りの対象が明確。 | 費用が高額。維持管理費や継承者の問題がある。 |
| 永代供養 | 寺院や霊園が永代にわたり管理・供養。合祀が基本。 | 5万円~150万円 | 継承者不要。費用を抑えられる。管理の手間がない。 | 一度合祀されると遺骨を取り出せない。 |
| 樹木葬 | 墓石の代わりに樹木を墓標とする。自然志向。 | 20万円~80万円 | 継承者不要の場合が多い。自然に還るイメージ。 | 樹木の成長など経年変化がある。冬場は寂しい印象になることも。 |
| 海洋散骨 | 粉骨して海に還す。専門業者への依頼が一般的。 | 5万円~30万円 | 継承者不要。維持管理費がかからない。故人の希望を叶えられる。 | 手元に遺骨が残らない。天候に左右される。お参りの場所が特定できない。 |
| 本山納骨 | 宗派の総本山に納骨する。信仰に基づく供養。 | 3万円~30万円 | 費用を抑えられる。宗派の開祖のもとで供養される安心感。 | 一度合祀されると遺骨を取り出せない。アクセスが遠方の場合がある。 |
最適な手元供養のやり方を見つけるには

- 手元供養は故人を身近に感じられる心温まる供養の形
- やり方に厳格な決まりはなく故人を想う気持ちが最も大切
- メリットは故人との繋がりを感じられお墓の費用や管理負担を軽減できる点
- デメリットは親族の理解が必要なことや自身の死後の遺骨の管理問題
- 供養品にはミニ骨壺や遺骨アクセサリー、ミニ仏壇など多様な種類がある
- 自分のライフスタイルや故人のイメージに合わせて供養品を選ぶことができる
- 何を置くかは基本的に自由で五供を参考にしたり故人の写真を飾ったりできる
- 遺骨の自宅保管は法律上「埋葬」に当たらず全く問題ない
- 自宅の庭など許可のない場所に遺骨を埋めることは法律で禁止されている
- 分骨も仏教的に問題はなくお釈迦様も分骨されている
- 手元供養は基本的に宗教や宗派を問わず行える
- 菩提寺がある場合は事前に住職へ相談することが望ましい
- 遺骨の保管ではカビと紛失のリスクに注意が必要
- 風通しが良く湿気の少ない場所に保管し密閉性の高い容器を選ぶ
- 分骨した場合に残った骨は永代供養や樹木葬、散骨などの方法で供養する
この記事では、手元供養のやり方について、様々な角度から解説してきました。やり方に厳格な決まりはなく、費用や管理の負担を減らせるうえに、故人との繋がりを感じることができる点が大きなメリットですね。一方で親族の理解が必要であったり、自身の死後の遺骨の管理問題など、難しい点があることも事実です。ご自身やご家族にとって最適な形が見つかるといいですね。



